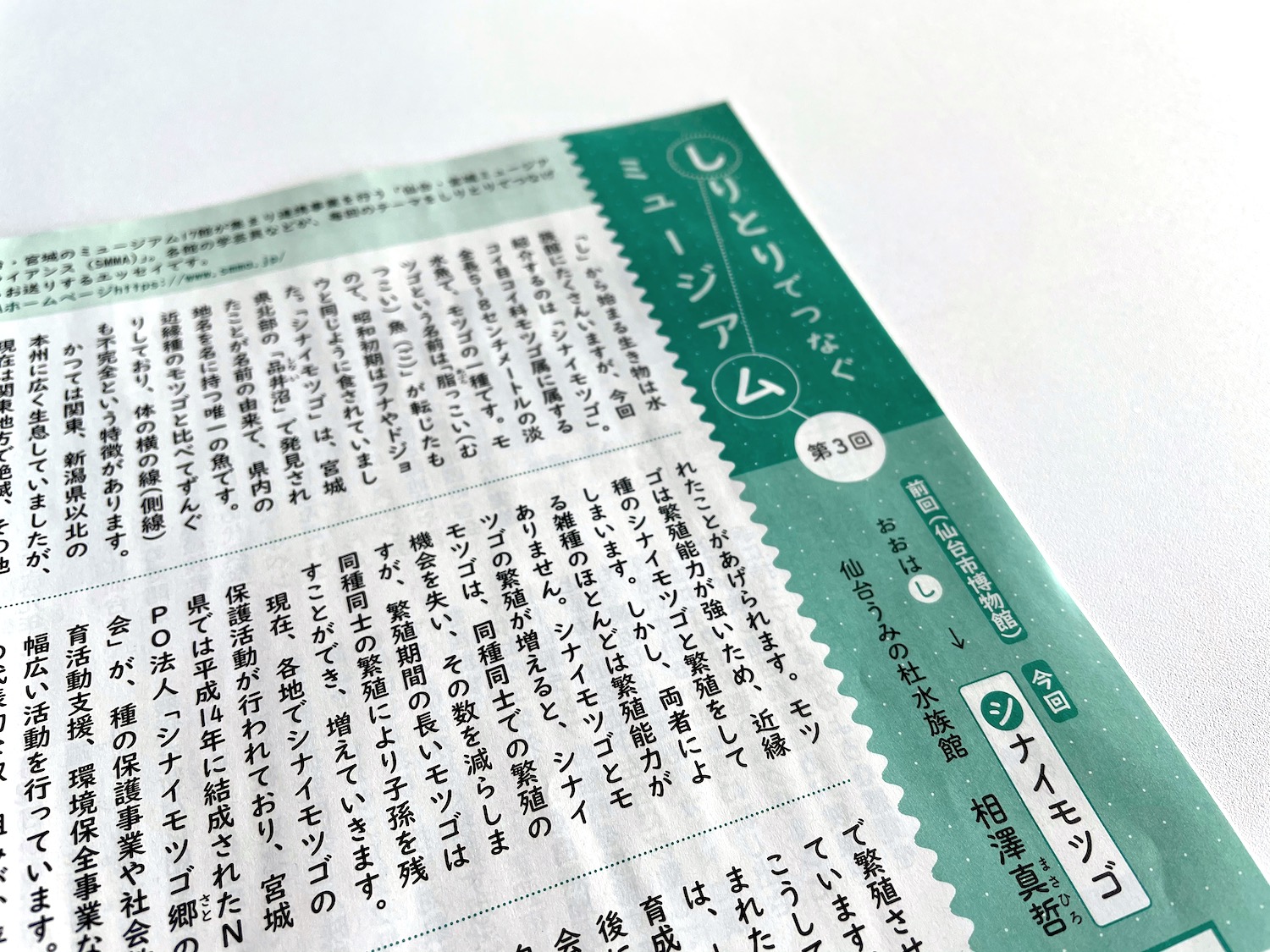ARTICLE
2012/04/17
「花」と文学
今年は四月になっても風が冷たい日が多く、春が完全に訪れるのはまだ少し先という感じがします。桜の開花も例年より少し遅めと伝えられています。
奈良時代には「花」といえば「梅」を表すのが一般的だったそうですが、次第に「桜」のことを指すようになりました。いにしえの文学作品にも、「桜」を詠んだ和歌が数多く残されています。
◯「花」を詠んだ和歌
花を詠んだ和歌は枚挙にいとまがありませんが、よく知られるものに次の二首があります。
「久方のひかりのどけき春の日にしづ心なく花のちるらむ」(紀友則)
注釈:「こんなに陽の光が穏やかにさしてくるのどかな春の日に、どうしてこうもせわしく桜の花は散っていくのだろうか」
「世中にたえてさくらのなかりせば春の心はのどけからまし」(在原業平)
注釈:「この世の中から、すっかり桜がなくなってしまえば、春という季節も心穏やかにすごすことができるだろうに(桜が咲くから心が乱れて落ち着かないことだ)」
どちらも、桜の美しさに惹かれるあまり乱れる心の有り様を詠んでいます。桜を詠んだ歌は、単にその美しさを寿ぐだけのものではありません。上記二首のような心の有り様を詠んだものや満開の後の散りゆく姿に思いを馳せたもの、桜を見る自分自身の心を投影したものが名歌として伝えられているのです。
◯桜を詠んだ歌人・西行
平安末期から鎌倉時代を生きた歌人・僧侶の西行は桜を詠んだ歌を多く残していますが、なかでも知られているものに次の歌があります。
「ねがはくは花のしたにて春しなんそのきさらぎのもちづきのころ」
注釈:「もし願いがかなうなら、桜の花の樹の下で、お釈迦様が入滅した時期と同じ春の日に穏やかに死にたいものだ」
旧暦で如月の望月(2月15日)は現在の3月から4月にあたり、釈迦が入滅した日とされています。自分の理想とする死のあり方を釈迦の入滅と桜に重ねて詠んだこの歌は、いわゆる「辞世の歌」ではありませんでしたが、この歌を詠んだ数年後、西行が望んだとおり旧暦2月16日に亡くなったという史実には不思議なものを感じます。
西行にはもう一つ面白い歌があります。
「花見にとむれつつ人のくるのみぞ あたらさくらのとがには有りける」
注釈:「花見をしようと大勢で人が押しかけてきて騒々しい。これは桜の花が美しいゆえの罪である」
花見客の騒々しさに苦り切っている西行の様子が目に浮かび、ちょっと苦笑してしまいます。現代の私たちにも思い当たる一首です。
◯小説に描かれた「桜」のイメージ―梶井基次郎と坂口安吾
梶井基次郎「桜の樹の下には」(1928年)は、桜がこの上なく美しいのは、その樹の下に屍体が埋まっているからだという空想に駆られる男のモノローグによる短編です。この世のものとは思えない桜の美しさに堪えられず、その一本一本の樹の下に屍体が埋まっているという光景をイメージすることで、この美しさにかろうじて耐えるという、病的なまでの男の神経が一人称で語られます。
もう一つ、坂口安吾「桜の森の満開の下」(1947年)は、十二世紀の鈴鹿峠の山賊の物語。山賊は峠の山も谷もすべては自分のものだと思っていたが、満開の桜の森だけは人間の心を狂わせるものと恐れ、近づかないようにしていました。ある日いつものように旅人を襲い、そのうちの女を自分の妻にするが、この女は恐れることもなく着いてきたばかりか、山賊に自分以外の女房を次々に殺させます。山賊はこの妻とともに都に出ますが、次第に妻の残酷さに嫌気がさし、また都にも馴染めず、とにかく山に帰ることにしました。山賊が妻を背負って山に戻ると桜の森は満開であったが、山に戻った嬉しさから満開の桜を恐れることもなくゴーゴーと音の鳴る桜の森を抜けていきます。しかし、途中で振り返ると鬼婆が追いかけてきます。首を絞めてくる鬼婆を必死で振り払い、逆にその首を締め上げた山賊が気がつくと、首を絞めたのは背負っていた妻でした。山賊は桜吹雪の中、声を上げて哭きます……。
「桜」をテーマにした文学作品はほかにもありますが、この二作品ほどよく語られるものはないでしょう。どちらの作品も、桜の花に「死」のイメージを重ね合わせ、人の心を乱す桜の「狂気」をモチーフとした名作です。
さて、仙台文学館の野趣あふれる敷地にも、一本の山桜の樹があります。先日の暴風で、枝が折れた樹もあったのですが、この山桜は無事でした。

Fig.1 仙台文学館敷地の山桜 撮影:佐々木隆二
華やかな桜並木とは違って、一本すっきりと経つ山桜の樹もまた、風情のあるものです。松尾芭蕉は次のような俳句を残しました。
「さまざまのこと思い出す桜かな」
桜を見て心に思うことは人それぞれ違うもの。今年は一人静かに自分の心に思いを馳せながら、桜を眺めてはいかがでしょう。
仙台文学館 学芸室長 赤間亜生